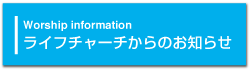デイリーディボーション 10月5日(木)
誰でも気軽に集える、明るく、カジュアルな雰囲気の教会です。
デイリーディボーション 10月5日(木)
2017年10月4日(水)
【通読】
マタイの福音書 21:12-13
12それから、イエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちをみな追い出し、両替人の台や、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。13そして彼らに言われた。「『わたしの家は祈りの家と呼ばれる』と書いてある。それなのに、あなたがたはそれを強盗の巣にしている。」
【ポイント】
①素晴らしいサービス?
当時のユダヤ教の制度では、献金のためには神殿用の貨幣を用いることが義務付けられていました。また、動物の捧げ物については、「傷のない」動物を捧げるように律法に定められていました(例:レビ記1:3)。ですから、エルサレム巡礼を楽しみに遠方から集まってきたユダヤ人にとっては、神殿の中で「両替」や「傷のない動物の販売」は大変便利なサービスだったわけです。特に、動物に関しては、旅の途中で死んでしまったり、怪我をしてしまっては捧げ物として受け取ってもらえないので、高い値段を払っても、そのほうが得でさえあると感じていたのではないかと思います。
②誰に対するサービスなのか?
現代においても、この一点について絶対に勘違いをしてはなりません。英語では「礼拝」を「(ワーシップ)サービス」という言い方をします。しかし、この「サービス」は教会が人々に提供するサービスではなく、私たちが神様にお捧げするサービスの意味なのです。つまり、サービスを受けるのは人ではなく神様だと言うことです。
ところが、神殿では人々のニーズに応えるサービスを充実させ、人々からも喜ばれ、祭司たちも利益を得るという行為一般化していたのです。この世の価値観からすれば、サービスを提供する側も受ける側も喜んでいるのですから、神殿での商売は倫理的で健全なビジネスだと結論付けられるかもしれません。しかし、あろうことか神様に仕えるはずの祭司たちから「神様に喜ばれる」という観点が欠落してしまったのです。
現代の教会も「人に喜ばれること」「人のニーズに応えること」が、神様の前では必ずしも「良いこと」ではない可能性があることに気が付かなければなりません。
ライフチャーチ
大谷信道