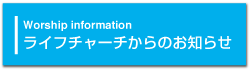デイリーディボーション 8月10日(木)
誰でも気軽に集える、明るく、カジュアルな雰囲気の教会です。
デイリーディボーション 8月10日(木)
2017年8月10日(木)
【通読】
マタイの福音書 14:13-14
13イエスはこのことを聞かれると、舟でそこを去り、自分だけで寂しい所に行かれた。すると、群衆がそれと聞いて、町々から、歩いてイエスのあとを追った。14イエスは舟から上がると、多くの群衆を見、彼らを深くあわれんで、彼らの病気をいやされた。
【ポイント】
①イエス様の「あわれみ」を感じる
イエス様はバプテスマのヨハネ処刑について、またヘロデがイエス様がバプテスマのヨハネのよみがえりであると思い込んでいることを聞きました。つまり、ヘロデの殺意が自分にも向けられていることを知られたわけです。そこで、イエス様は一旦ヘロデの支配地域から離れるために「舟でそこを去り、自分だけで寂しい所に行かれた」と思われます。逮捕や死を恐れ、逃げるためではなく、天の父から与えられた計画を、計画通りに成し遂げる邪魔をさせないためでしょう。(マタイ26:18)
ところが、群衆がイエス様の後を追ってきてしまいます。これでは「寂しい所」に退く意味が全くなくなってしまいます。イエス様を捕まえたいと思っている人がいれば、いとも容易にイエス様を見るけることができてしまうからです。
しかし、イエス様は群衆に腹を立てるどころか、「深くあわれまれた」のです。イエス様が置かれている状況などお構いなしで、自分のいやしのことしか考えていない人々、いやされてもイエス様をメシアとして信じ、従うことがない人々に対し、イエス様は「あわれみ」を覚え、危険を承知の上で彼らをいやされたのです。
②イエス様の視点で見る
当時のパリサイ人、律法学者に欠けていたものは、この「あわれみ」でしょう。別の言い方をすれば「罪深いものを愛する心」でしょう。聖書の律法、聖書の教えを「正論」として用い、罪深いものを裁くことは誰にでもできることです。しかし、イエス様は、天の父は正論で人を裁く方ではなく、罪人をあわれむ方であることを明らかにされたのです。
クリスチャンの成長がイエス様に似た者となることであるとすれば、この「あわれみ」を身につけることも成長の一つなのです。逆に、正論で相手をさばく人は、本人は聖書的な観点から他者を導いているつもりでいたとしても、そのような人の信仰は未熟であるということなのです。正論で相手(親、教師)をさばくことは、思春期(成長期)の子どもたちの特徴ですね。残念ながら、ここで成長が止まってしまっている大人がたくさんいるのです。「正論」を知っていることが成長だと勘違いしてしまっているのです。本当の成長は、相手の弱さ、不完全さを受け止め、理解してあげること、相手の成長を忍耐強く見守ることであること、つまり、成長には「あわれみ」「赦し」「愛」が不可欠であるということを、イエス様の生き様から知ることができるのです。
また、私たちは、自分がイエス様の「あわれみ」「赦し」「愛」ゆえに、救われていることを忘れてはならないのです。
ライフチャーチ
大谷信道