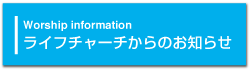デイリーディボーション 8月23日(水)
誰でも気軽に集える、明るく、カジュアルな雰囲気の教会です。
デイリーディボーション 8月23日(水)
2017年8月23日(水)
【通読】
マタイの福音書 15:32-39
32イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。「かわいそうに、この群衆はもう三日間もわたしといっしょにいて、食べる物を持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。」33そこで弟子たちは言った。「このへんぴな所で、こんなに大ぜいの人に、十分食べさせるほどたくさんのパンが、どこから手に入るでしょう。」34すると、イエスは彼らに言われた。「どれぐらいパンがありますか。」彼らは言った。「七つです。それに、小さい魚が少しあります。」35すると、イエスは群衆に、地面にすわるように命じられた。36それから、七つのパンと魚とを取り、感謝をささげてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして、弟子たちは群衆に配った。37人々はみな、食べて満腹した。そして、パン切れの余りを取り集めると、七つのかごにいっぱいあった。38食べた者は、女と子どもを除いて、男四千人であった。39それから、イエスは群衆を解散させて舟に乗り、マガダン地方に行かれた。
【ポイント】
①異邦人の救い主
実は、イエス様は依然として異邦人の住む地域にいます。カナンの女性の娘のいやし、昨日の群衆のいやしも異邦人の地域で行われていました。この直前(14:13-21)に5,000人の給食のエピソードが記されているのに、再び同じよう給食の話が載せられているのに違和感を覚える人もいると思いますが、この二つの出来事には大きな違いがあります。それは、今回はイエス様が「異邦人」に対して給食の奇跡を行われたということです。
イエス様が異邦人をも救いたいと思われていたという事実は極めて重要です。なぜなら、使徒の働きを読んでも、最初のクリスチャン達が異邦人の救いの計画について正確に理解できていない様子を見ることができるからです(例:使徒15章)。恐らく、マタイは、異邦人のいやしや給食の出来事などをの出来事から、イエス様(神様)が異邦人の救いの計画を持たれていたことを明確に記すべきであると考え、一見すると似たように見える二つの給食の奇跡を、全く別の意味を持つ出来事として、その両方を記録したのでしょう。
現代の日本でも、「キリスト教は外国の宗教」と感じている人が少なくないでしょう。しかし、イエス様がユダヤ人だけでく、全人類の救い主であることは、聖書を見れば明らかなのです。家族や友人に福音を伝えるときにも、イエス様が異邦人である私たちも愛し、救いに導きたいと思われている事実を分かち合うことがとても大切だと思います。
ライフチャーチ
大谷信道