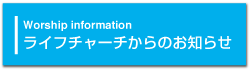デイリーディボーション 11月13日(木)
誰でも気軽に集える、明るく、カジュアルな雰囲気の教会です。
デイリーディボーション 11月13日(木)
2014年11月13日(木)
2コリント 11:26-28
26幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、にせ兄弟の難に会い、27労し苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。28このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心づかいがあります。
【ポイント】
①「親の心子知らず」
このポイントについては以前も学んだと思います。「親の心子知らず」ということわざがありますが、これは時代や地域に関係なく普遍的な現象なのだと思います。しかも、それは関係だけに限定されるものではなく、経営者と社員、上司と部下、教師と生徒、部活動の部長と部員、牧師と信徒などの間にも起こるのです。さらに、互いにわからない部分があるという点では「子の心親知らず」というような現象も起きています。ここで重要な事はこのような相互理解のギャップというものが常に存在していることを認めることです。つまり「なんでうちの子は親の気持ちがわからないのだろう?」「何で部下は自分の気持ちがわからないのだろう?」と腹を立てたり、嘆いたりすることを止めるということなのです。自分が子どもだった時のこと、新入社員だった時に感じていたことを思い出せば、自分が親の思いをどれだけ分かることができなかったのか、自分が上司の苦労や立場を理解していなかったのかを思い出すことができるはずです。つまり、自分がそうでなかったのだから、自分の子どもや部下に自分の思いを十分に理解できないという事実を受け入れ、相手は自分の苦労を理解しているべきだという要求を捨て去ることが大切なのです。ここが、相互理解のスタート地点なのではないでしょうか。
②パウロの柔和
パウロはコリントの教会の人々が、パウロが実際にどれだけの犠牲を払い、どれだけの苦難の中で伝道を続けているのかを理解していないことを知っていました。もし、コリント教会の人々がパウロの苦難を本当に知っていれば、彼の使徒としての資質、資格を疑うような行動には出なかったはずなのです。ですから、パウロは本当はわざわざ口に出したくない自分のキャリアや苦難について仕方なく説明しているのです。本当はコリントの教会の人々がパウロの生き様を見ることによって、彼が真実な使徒であることを理解して欲しかったのですが、それができない人々がたくさんいたのでしょう。しかし、パウロは「こんなことは口に出さなくても理解するべきだ!」というような傲慢な態度を取りませんでした。反対に、丁寧に説明する(ちょと皮肉も込められていますが)ことを選んだのです。親の上司も、自分がどれだけ苦労しているのかを子どもや部下に話したくないものです。でも心のどこかには、子どもの部下も自分のことを理解するべきであるという要求を持っているものです。そして、そのような思いを貯めこみ、限界を越えたときに爆発させてしまうのです。しかし、これはとても悪い方法ですね。相手のことを本当に愛しているのであれば、パウロのように、こだわりやプライドを捨て、柔和さをもって自分の思いを伝えることも大切なのです。
【祈り】
《ガラテヤ》
3だれでも、りっぱでもない自分を何かりっぱでもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。
4おのおの自分の行ないをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、ほかの人に対して誇れることではないでしょう。
5人にはおのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。
アーメン
ライフチャーチ牧師 大谷 信道