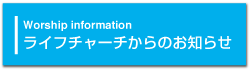デイリーディボーション 10月24日(金)
誰でも気軽に集える、明るく、カジュアルな雰囲気の教会です。
デイリーディボーション 10月24日(金)
2014年10月24日(金)
2コリント 9:11-12
10蒔く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなたがたにも蒔く種を備え、それをふやし、あなたがたの義の実を増し加えてくださいます。11あなたがたは、あらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して、神への感謝を生み出すのです。
【ポイント】
①永遠への投資
「投資」ということばを信仰の世界で使うことに違和感を覚える人がいることでしょう。しかし、ここでパウロが話している「蒔く」「種」「パン」の喩えは、当時の多くの人々が生活の糧を得ていた農業という産業の喩え(ここでは、小麦栽培でしょうか。)なのです。多くの収穫を期待するためには、多く蒔く必要があります。多く蒔くためには、前の年の収穫から売ったり、自分たちで消費したりしないで、種を大量に取っておく必要があります。それは、どれほどの量、割合だったのでしょうか。実は、1世紀の農業は現代のそれとは比べ物にならないほど効率の悪いものであったそうです。日本の小麦栽培の効率は極めて高く、1粒蒔くと、50粒程度の収穫ができるそうです。ですから、すべての種が発芽しするとしたら、全体の50分の1の量の種を残しておけば、次の年も同じ収穫量を見込めるわけです。
ところが、驚くことに古代においては、小麦は1粒蒔くと2粒程度しか収穫できないほど効率の悪い農業を行っていたそうです。農業技術の進歩は決して早くなく、1粒蒔いて3粒程度にまで向上したのだ10世紀、1粒蒔いて10粒収穫できるようになったのは、なんと19世紀に入ってからだそうです。つまり、1世紀の世界の常識では、毎年、同じ収穫を期待するためには、収穫した小麦の半分が消費用(パン)とし、半分を種としてとって置かなければなりませんでした。ですから、次の年の収穫量を増やしたいと思ったら、その年の消費分(パン)を減らし、種の分を増やす必要がありました。種は空から降ってくるわけではありませんから、「多く蒔く」人とは、自分の取り分を減らし、次の年の収穫のために投資する人を意味しているわけです。反対に、目先の利益のために、自分の消費分、出荷分を増やしてしまう人は、種の分が減り、収穫が減り続けるというスパイラルに陥ってしまうのです。
これが、パウロが話している農業の実態なのです。このような事実を知ると、パウロの種まきの話がだいぶ違うものとして見えてくるのではないでしょうか。この喩えが、霊的に何を意味しているのか、しっかりと考えてみましょう。
【祈り】
《2コリント9章》
6私はこう考えます。少しだけ蒔く者は、少しだけ刈り取り、豊かに蒔く者は、豊かに刈り取ります。
アーメン
ライフチャーチ牧師 大谷 信道