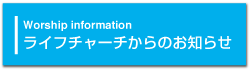デイリーディボーション 5月13日(月)
誰でも気軽に集える、明るく、カジュアルな雰囲気の教会です。
デイリーディボーション 5月13日(月)
2013年5月13日(月)
ヘブル人への手紙 9:1-5
1初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。2幕屋が設けられ、その前部の所には、燭台と机と供えのパンがありました。聖所と呼ばれる所です。3また、第二の垂れ幕のうしろには、至聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、4そこには金の香壇と、全面を金でおおわれた契約の箱があり、箱の中には、マナの入った金のつぼ、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。5また、箱の上には、贖罪蓋を翼でおおっている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては、今いちいち述べることができません。
【ポイント】
旧約の律法、種々の儀式が「キリストの影」であるとすれば、キリストをより深く知るために重要な情報があるのです。ヘブル書の著者の姿勢からも、彼は決して旧約の律法、幕屋を無意味なものとして切り捨てているのではいことが明らかです。反対に、そこに表されている神様の美しさ、荘厳さ十分に理解していると思われます。だからこそ、それにはるかに優るキリストの素晴らしを、なんとか説明しようと、幕屋についての簡単な設計を加えているのです。良い機会ですので、出エジプト記の25~40章を読むことをお勧めします。
①神様の聖さを知る
神様がイスラエルの民に要求した「聖さ」を知ることは極めて重要です。汚れたままで主の臨在に触れることは「死」を意味しました。ですから、祭司達以外が不用意に神様に近づかないように警告がなされました。「これからはもう、イスラエル人は、会見の天幕に近づいてはならない。彼らが罪を得て死ぬことがないためである。
」(民数記18:22) さらに、祭司たちに対しても「アロンとその子らは、会見の天幕に入るとき、あるいは聖所で務めを行なうために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らが咎を負って、死ぬことのないためである。これは、彼と彼の後の子孫とのための永遠のおきてである。
」(出エジプト28:43)と警告が与えられています。
この事実は今日も変わることはありません。今日も罪に汚れた者は神に近づくことはできません。そして罪の汚れを持ったままで神の臨在に触れることは死を意味します。新約時代に入って、この原理が自動的に廃棄されたなどと考えてはならないのです。
②イエス様の犠牲の価値を知る
「神様の個人的な関係を深めましょう!」などという励ましは、本来バカバカしいものである。例えば、飢餓に苦しむ人々が、日本の食卓で親が子どもに「もっとたくさん食べなさい!」「好き嫌いしちゃだめ!」などと教えている姿を見たとしたら、どう思うでしょう。学校教育を受けることができない国の子どもが、「もっと勉強しない」と怒られている先進諸国の子どもの姿をみたらどのように思うでしょうか。あまりにバカバカしくて、言葉も出ないかもしれません。
全く同じように、神様を求めながら、その罪のために個人的な関係を深めることが許されなかった旧約時代について知らない私たちは、神様と個人的に交わることの本当の価値を知ることは難しいのです。「イエス様と個人的な関係を深めましょう!」などと言われているという事実は、イエス様の割かれた体と流された血、経験された永遠の死の苦しみをの意味も、価値も分かっていないという事を露呈していることになるわけです。神様のとの個人的な関係を持つことが「当たり前」のようになってしまうと、それを求める思いも無くなってしまうのです。
そのような状態に陥ることがないように、キリストの新しい約束がなかった時代のことを学び続ける必要があるのです。
【祈り】
《ローマ8章》
1こういうわけで、今は、キリスト・イエスにある者が罪に定められることは決してありません。
2なぜなら、キリスト・イエスにある、いのちの御霊の原理が、罪と死の原理から、あなたを解放したからです。
ライフチャーチ牧師 大谷 信道